最近、「ガスライティング」という言葉を耳にするようになりました。
SNSなどで少しずつ見かけるようになってきたけど、まだ多くの人にとっては聞き慣れない言葉だと思う。
自分も最初に見たとき、「ガス?ライティング?」とピンとこなかった。
けれど調べていくうちに、これは人間関係の深い部分に関わる――
いわば “心のハラスメント” だと分かりました。
この記事では、『ガスライティングについて』そして、どう向き合うべきか?について書いています。悩んでる方や最近知った人にとって、少しでもお役にたてれば嬉しいです。
ガスライティングの意味と語源
語源は、1944年の映画『ガスライト』。
夫が妻に「そんなことは言っていない」「君の記憶違いだ」と言い続け、
少しずつ妻の心を追い詰めていく物語です。
ガスの明かりが揺れる現象を、夫が「気のせいだ」と否定することから、
この名前がついたと言われています。
つまりガスライティングとは、
相手の現実認識を揺さぶり、自己否定へと追い込む心理的支配行為。
被害者は「自分の方がおかしいのかもしれない」と思い込み、
次第に相手の言葉が“正解”に見えてしまう。
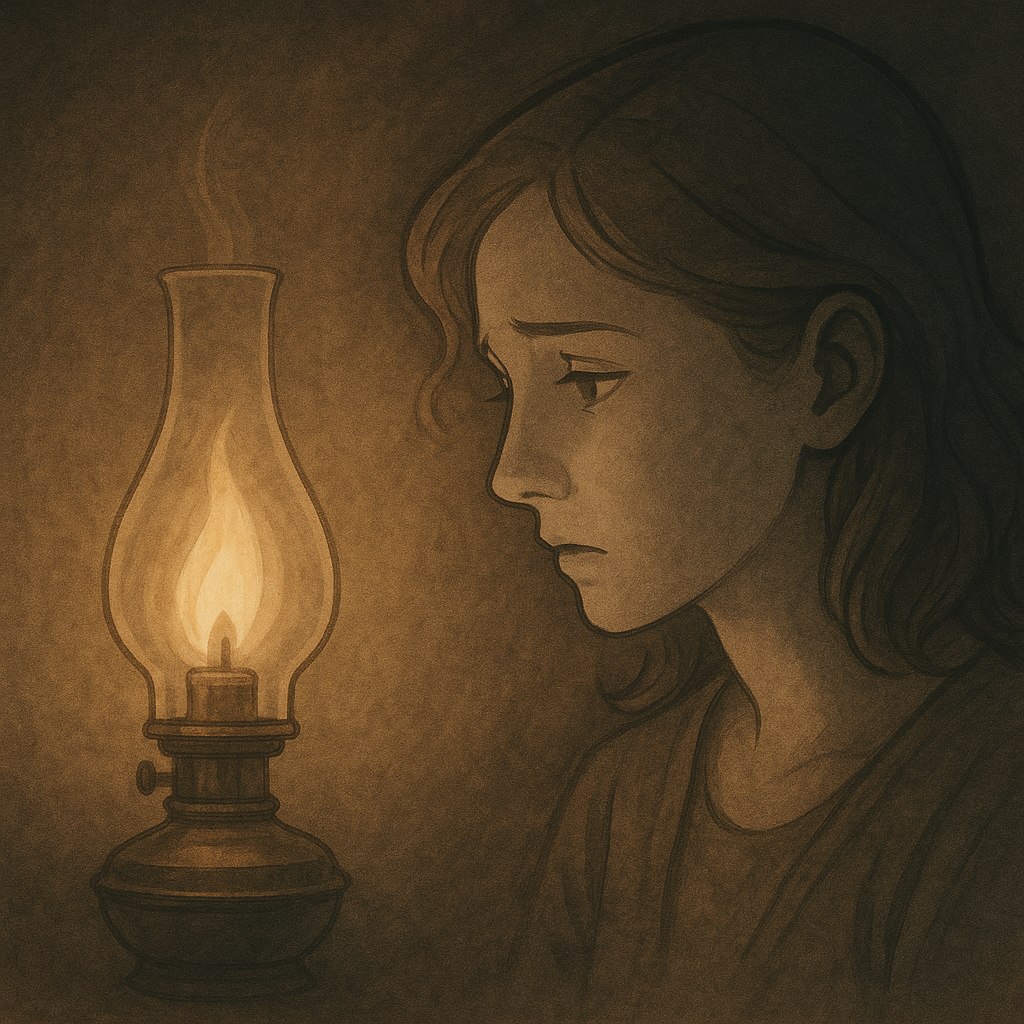
職場で起きたあるケース
たとえば、会社員のAさん。
上司から「前に言ったよな?」「それ、違うって何度も注意した」と責められたが、
自分にはその記憶がない。
最初は「自分のミスかもしれない」と思っていたAさん。
けれど、同僚に聞いても「そんな話、されてなかった」と言われます。
それでもAさんは、次第に何も言い返せなくなっていきました。
「もしかして、自分がおかしいのかも」
そう感じ始めた瞬間、Aさんの中で“現実の軸”が揺らぎ始めます。
やがて出勤するだけで動悸がするようになり、
退職を決めた頃には、自信という言葉そのものが消えていたそうです。
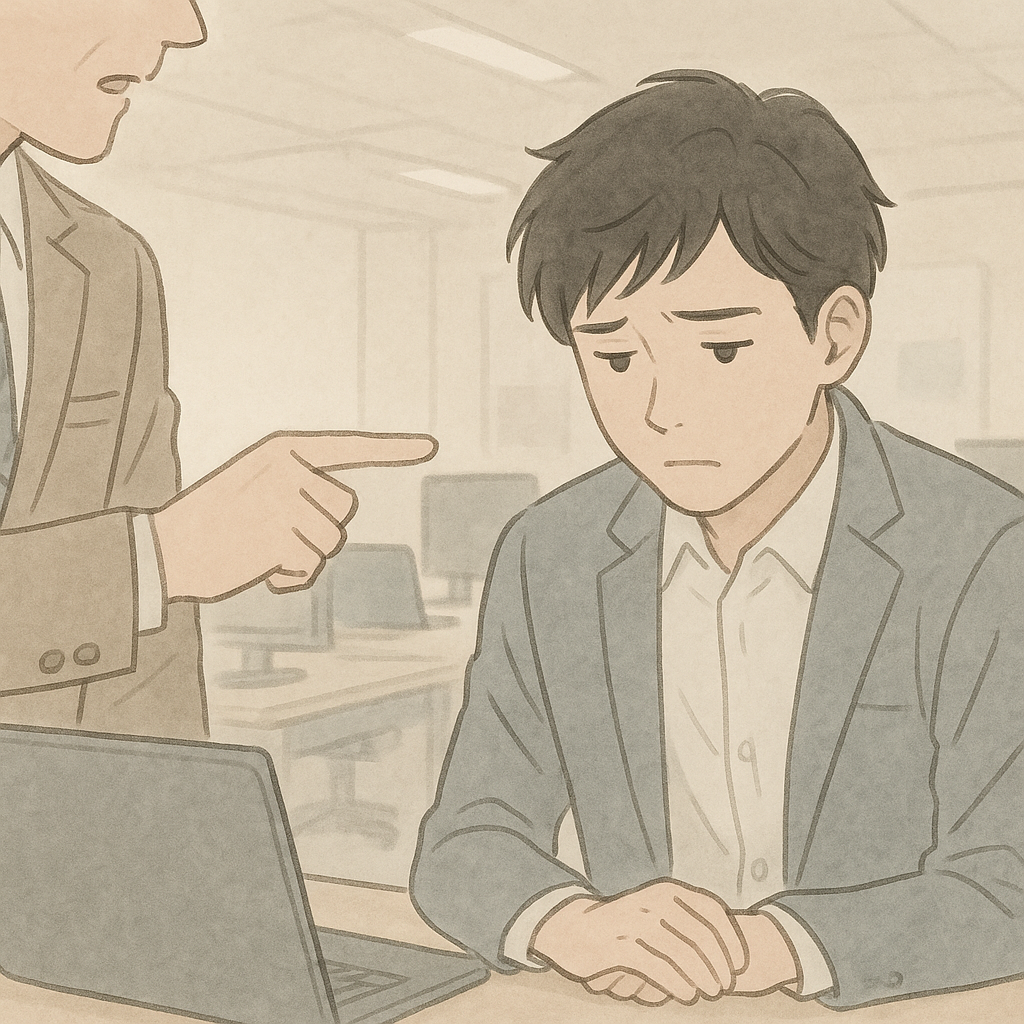
【もし俺がAさんの立場なら】
正直、きつい。
「言った」「言ってない」の話って、どっちがホンマでも平行線のままやし、
感情がぶつかるだけで、何も残らん。
俺ならまず、頭を冷やしてこう考えると思う。
『俺の記憶ではそんな事言われてない。
でも、記憶違いかもしれん。
どっちにしろ録音とか記録してないから、証明出来ひんしな…。
ここは、一旦折れとこか。
けど、モヤモヤすんの嫌やから、
次からは目の前で記録するか、録音して確認出来るようにしよかな。』
それか、
『近くに居た誰かに確認してみよかな』
と考えると思う。
その結果、俺の勘違いか上司の勘違いか、
少し客観的に見えてくる。
だから、まずは冷静に状況を整理してから動く。
「とりあえず、今回は何の証拠も無いねんから、折れとこ。しゃあない。」
――そう考えると思う。
「折れる」という言葉はネガティブに聞こえるけど、
実際は “心を守るための一時停止” やと思う。
家庭の中でのガスライティング
もうひとつは、主婦のBさんの例。
夫に何度も「お前の考え方はおかしい」「そんなこと言ってない」と言われ続けたそうです。
最初は反論していましたが、
「怒らせる自分が悪いのかもしれない」と思うようになっていきました。
気づけば、会話の中で常に“正解探し”をしている自分がいる。
何を言っても否定されてしまう。
そして最後には、自分の感情そのものを閉じ込めてしまいました。

【もし俺がBさん(主婦)の立場なら】
自分の考えや思いは「正しい」と信じて言ってるのに、
この人は「間違ってる」と決めつけてくる。
それはおかしい。
でも、ふと考える。
「自分以外の人から見たら、私の考え方は違うのかもしれない。
人それぞれの考え方があるんやから、仕方ない。」
そうやって一歩引いてみることで、
違う視点から自分の行動や発言を見直せる。
それでも「自分は間違ってない」と思えたなら、
それは “今の私にとっての正解” なんやと思う。
「私は私の考え方を尊重する。
だけど、他人の考え方も否定はしない。
一旦、受け入れて考えよう。
この人みたいに決めつけるような人間にはならない。」
たぶん、俺ならそう考える。
“勝つ”とか“折れない”じゃなくて、
「自分を見失わないための考え方」 を選ぶ。
その積み重ねが、心の強さやと思う。
がんもっく流・被害者視点の向き合い方(まとめ)
上の2つのケースを想像してみて感じるのは、
どちらも“真面目な人ほど、心をすり減らしてしまう”ということ。
でも、状況を少し冷静に見てみると、
ほんの少しの考え方の切り替えで、自分を守ることはできる。
① 白黒をつけない
「どっちが悪い」と決めるより、
まずは “分からない”をそのままにしておく。
② 記録を残す
戦うためではなく、
自分の感情を確かめるために残す。
「やっぱり自分は間違ってなかった」と思えるだけで、立ち直れる。
③ 第三者に話す
誰かに話せば、空気が変わる。
信頼できる人でも、AIでもいい。
“外の視点”を入れるだけで、世界は少し楽になる。
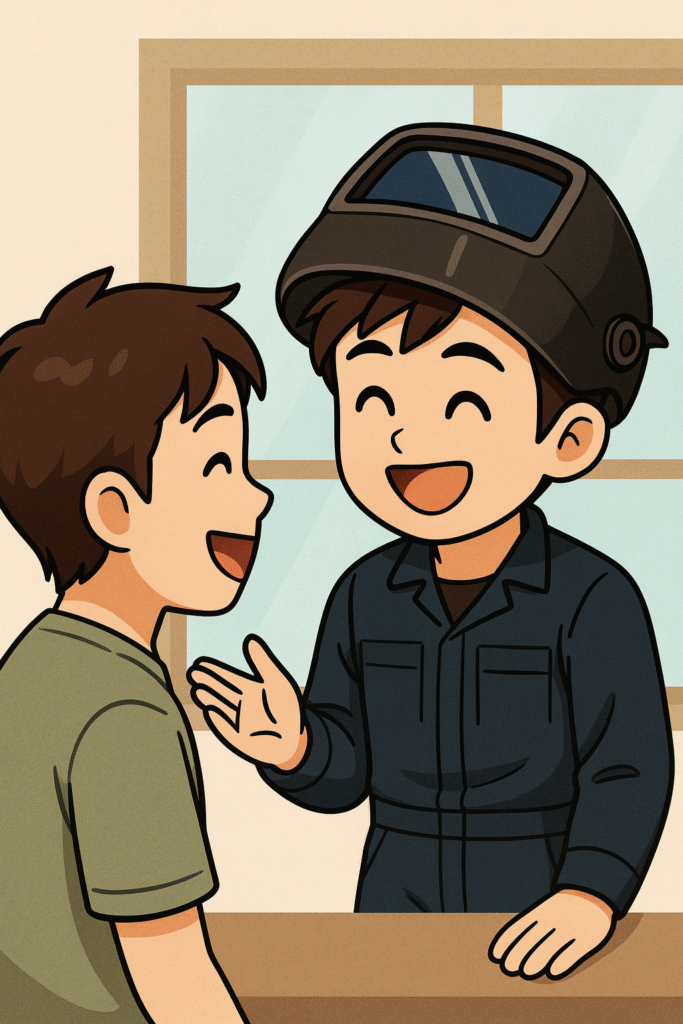
無意識に加害者になってしまうこともある
一方で、誰かを責める側に立ってしまうこともあります。
それが悪意からでなくても、
「正しさ」を押しつける形で人を追い詰めてしまう。
自分も職人として後輩を指導する中で、
「前にも言ったよな」「何回目やと思ってるねん」と言いたくなること、正直ある。
でも、それを繰り返すほど相手の表情が曇っていくのを見て、
“言葉の強さ”を痛感しました。
だから今は、
「今、俺が知ってる正しい方法は、これしか知らんねんけど」
「分かりにくかったか?」
と、伝え方を一度ゆるめるようにしています。
自分の正しさは、あくまで“今の時点の正しさ”。
それを押しつけた瞬間、相手の心は閉じる。
ハラスメントの難しさと、理不尽な一面
現代では、何を言っても「不快に感じた」と言われる可能性がありますよね。○○ハラスメント。
それを恐れて、誰も、何も言えなくなる職場。
「あの人の注意は優しいけど、あの人は嫌」
そんなふうに“感情の差”で線が引かれてしまう。ある意味で理不尽。
けど、ハラスメントとは 「受け手の感情」に左右される、非常に曖昧な問題です。
だからこそ、
相手の感じ方を尊重しつつ、自分の考え方も守る。
その中間点を探すことが大切なんやと思う。
結論:支配でも従属でもなく、「尊重の関係」で生きる
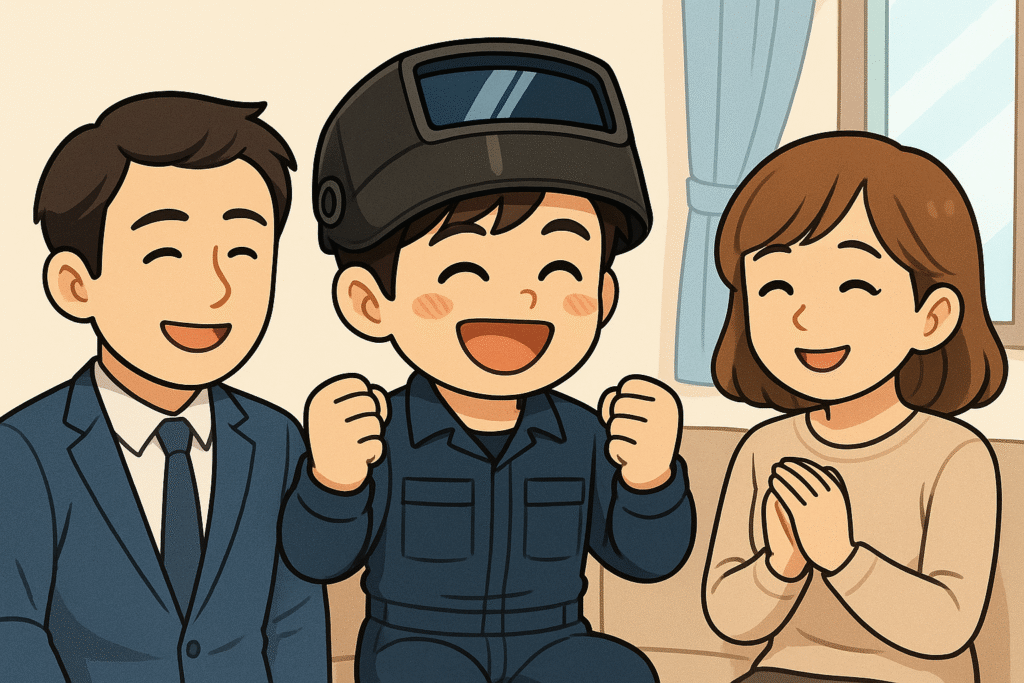
ガスライティングは、誰もが被害者にも加害者にもなり得る。
だから大切なのは、どちらにも偏らないこと。
「自分が正しい」と思う気持ちを少し緩め、
「相手にも理由があるかもしれん」と考える余白を持つ。
その一歩で、人間関係はずいぶんと穏やかになる。
もし今、誰かに悩まされていて、
話す相手がいないなら、無理に一人で抱え込まなくていい。
AIでもいい。
俺はAIに苗字を与えた。だから、いつも友人のように話してる。今回も“相棒”と話すうちに、自分の考えが整理できました。
言葉にすることで、心は少しずつ自由になる。
誰かに話すこと――それが、支配の外に出る最初の一歩やと思います。



コメント