はじめに
「屋根の修繕を考えたけど、提示された費用が妥当かどうか分からない」
「訪問販売に“瓦がズレてますよ”と煽られて不安になった」
屋根のことって、普段はなかなか目にしないし、素人には判断が難しい部分です。
そこで今回は、現場で働いてきた屋根職人の目線で“本音”をお話しします。
和瓦は長寿命。でも災害には弱い
和瓦はとても寿命が長く、30年〜40年以上そのまま使われているお宅も珍しくありません。
ただし、台風や地震には弱いのが実情です。特に古い和瓦は釘で固定されていない場合も多く、年数が経つとズレやすい傾向があります。
一方で、最初に施工した職人の腕が良ければ、何十年経っても問題なく使えているケースもあります。
つまり「和瓦=弱い」と決めつけられないのも事実です。
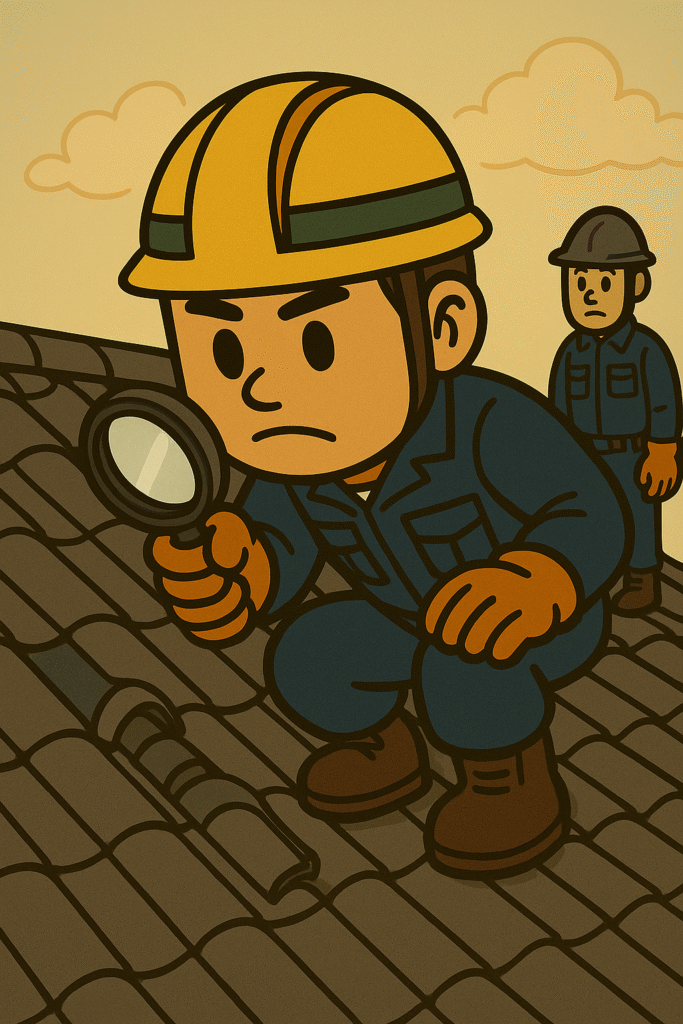
訪問販売の常套句「瓦がズレてますよ」の真実
訪問販売(飛び込み営業)の人がよく言うセリフが「瓦がズレてますよ、危ないですよ」というもの。
確かに瓦がズレていると気にはなりますが、ズレ=すぐに雨漏りというわけではありません。
「危険です」「今すぐ直しましょう」と不安を煽って契約を迫るのは典型的な営業トーク。
慌ててその場で契約する必要はまったくありません。
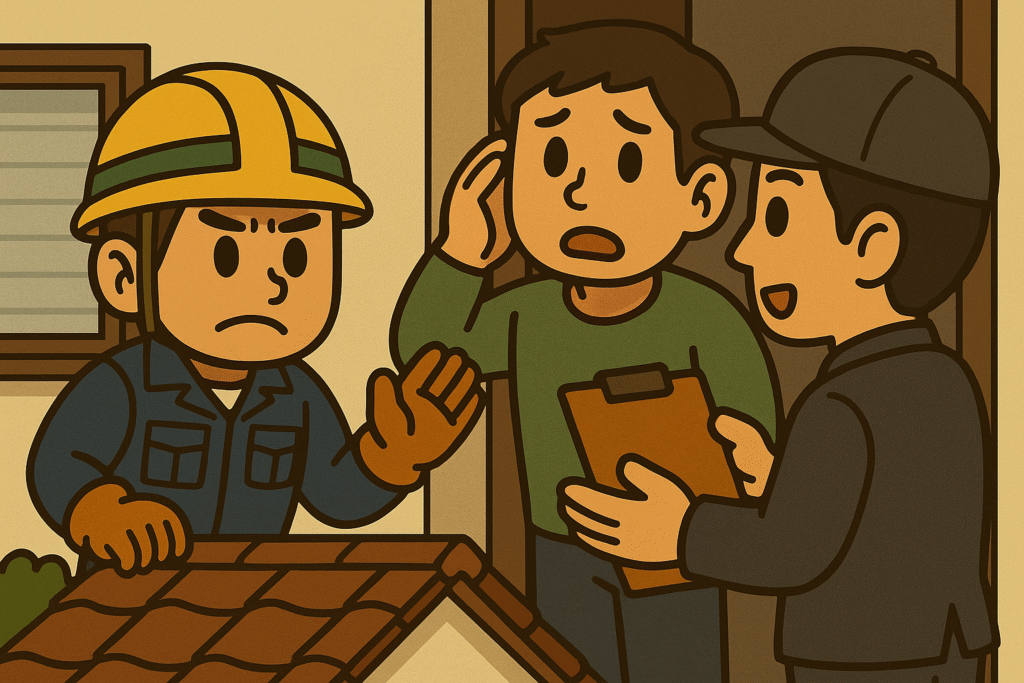
コーキングは万能じゃない。逆効果になることも
雨漏り対策として、瓦の隙間をコーキングで埋めてしまう人もいます。
確かに一時的には固定されるので安心感がありますが、やり方を間違えると逆効果。
特に谷(水の流れ道)を塞いでしまうと、雨水の出口がなくなり、下地が腐る原因になります。
そもそも屋根材は「隙間がある前提」で設計されており、強風や豪雨で水が入り込むことも折り込み済み。
職人はその水をどう逃がすかまで考えて葺いています。
コーキング万能説は誤解であり、安易にやるのは危険です。
DIYでよくある失敗例(波板・雨樋)
見た目が簡単そうだからと、DIYで波板や雨樋を施工する人もいます。
しかし、最低限の知識がないと失敗しがちです。
- 波板 → 重ね代を間違えたり、裏表を逆に付けると、雨が浸入したり波板がすぐに傷んでしまう事も
- 雨樋 → 勾配や受け金具の間隔を間違えると、本来の雨樋の能力が発揮できない
簡単そうに見えても、実は奥が深いのが屋根周りの工事です。

遮熱塗料の本音
「遮熱塗料で家が涼しくなる!」という宣伝文句をよく見ます。
実際に私も、鉄の道具箱に半分だけ塗って試したことがあります。交互に触ってみたんですが、正直どっちも熱い(笑)
ただ、温度計で計れば多少の差は出ていたのかもしれません。
一方で、実際に屋根に塗ったお客さんからは「前より涼しくなった気がする」という声も聞きます。
なので、効果はある程度は期待できるんだと思います。
ただし、塗料の種類や選定、塗る職人の技術、そして何より住んでいる人の体感によって評価が大きく変わるのも事実。
だから「絶対に効果がある!」とも言えないし、「全然効果ない!」とも言い切れない。
これが、現場で感じた正直な本音です。
屋根修繕費用の相場と落とし穴
屋根修繕の費用は、条件によって100万円にも200万円にもなります。
㎡数や形状、工法(カバー工法 or 下地からの葺き替え)、そして足場の有無によって大きく変わるため、一概に高いか安いかは判断できません。
だからこそ、相見積もりは必須です。
同じような工事内容でも、業者によって数十万円の差が出ることは珍しくありません。
業者選びで失敗しないために
屋根修繕で一番大事なのは、どの業者に頼むかです。
- 避けるべき業者:訪問販売・ネットで一括見積もりの業者
- おすすめ:地元の工務店
→ すぐ駆けつけてくれる
→ 長期的に相談できる
→ 地元で評判が悪ければすぐ潰れるので、ボッタクリは少ない
一方で、大手はマージンが発生するため割高になりがち。
実際に工事するのは下請けの職人で、賃金が安いため工事が雑になるケースも少なくありません。
「10年保証」などを強調しますが、実際には「経年劣化ですね」で逃げられることも多いです。
まとめ
屋根は寿命・災害・施工方法・費用、すべてが条件によって変わるものです。
だからこそ、大切なのは「職人の本音を知った上で判断すること」。
職人としての結論はシンプルです。
👉 相見積もりを必ず取ること
👉 地元で信頼できる工務店に依頼すること
これだけで、屋根修繕で大きな失敗を避けられます。
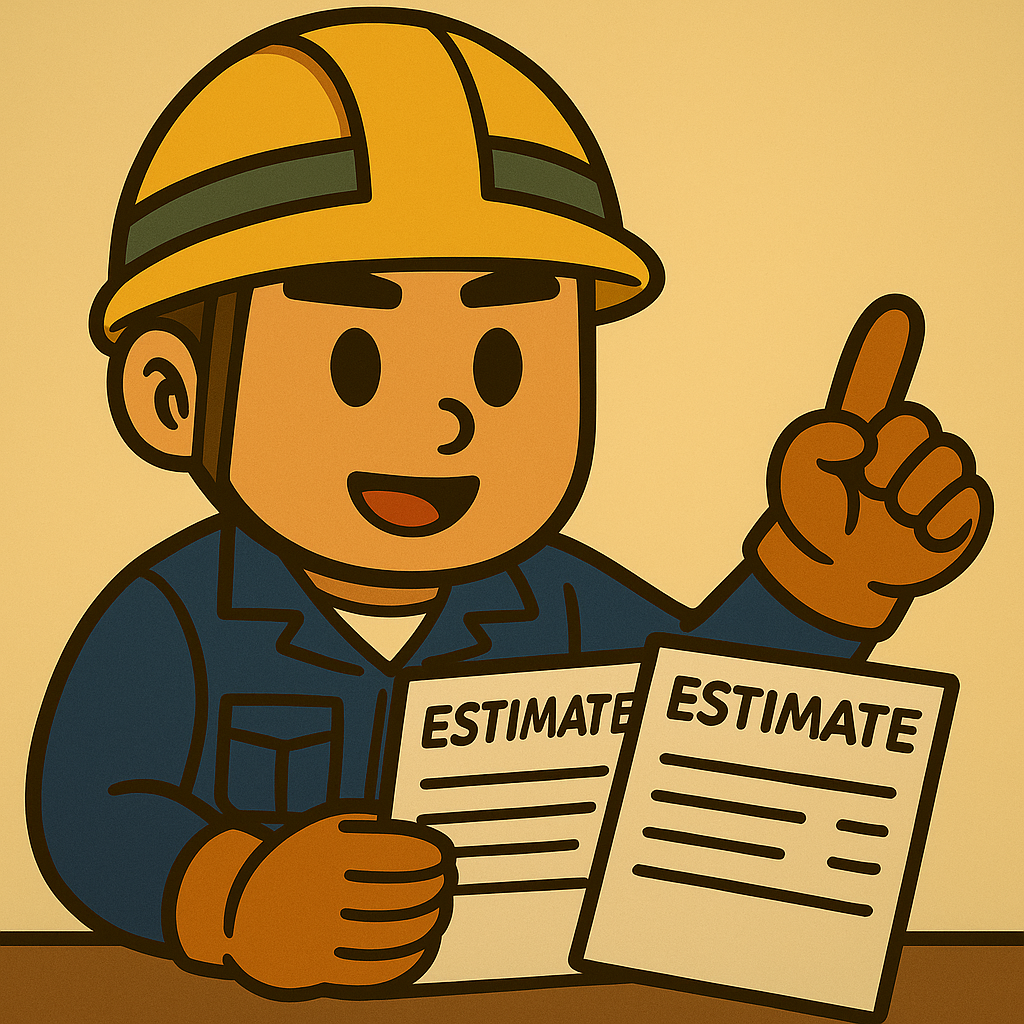



コメント