禁酒し始めた理由
最近、禁酒しております。節約と怪我の回復が目的です。
だいぶ前に痛めた肘の具合が悪く、仕事中も「痛みを我慢しながら作業する」ことが続いており、どうにか回復させる為に2回ほどステロイド注射を打ちました。
でも、効果は3ヶ月程度。また痛み出します。
この注射は何度も打つのは良くないらしく、医者に無理を言って2回目を打ってもらったので、さすがに3回目はアカンやろな、と思い、ロキソニンと湿布で耐えています。
出来るだけ負荷をかけないようにしていても回復の兆しが見えず、炎症が治まるように、酒をやめてみようと思ったのがキッカケです。

酒好きの自覚
禁酒してると言っても、実はまだ10日程です。
ただ、私は大の酒好き。毎日飲んでいました。それも20年以上。
日中は夏場でも無い限りほとんど水分を取りません。一日に500mlも飲んでないと思います。
その代わり、夜はお茶の代わりにビールという感じでした。
酷い時は缶ビール計算だと、一日3リッターくらい飲んでました。
昔の原付バイク並みです。それも一晩なんで、燃費めちゃめちゃ悪い原付バイク。
最近はかなり量を控えようと、缶ビールだと1リッターくらいまでにしていました。
充分、飲み過ぎだと言われることは分かっております。でも、私にとっては非常に抑えた量。
家計管理から気づいた異変
1リッターの減酒(?)生活に切り替えて1年ほど経ち、最近になってブログを始め、リベ大の家計管理なんかもチャレンジしていました。
支出を減らす。**一体何を削ればいいんだろう?**そんな贅沢なんかしてないけどなぁ。と、管理表を睨みながら、プシュっ、グビグビ。
コンビニ費が高い事に気づきます。これは、減らさないと。
そう思って、ブログ記事にも書き、減らす為の努力を始めます。
タバコも吸うので、これも減らさないとなぁ。
いきなり禁煙する自信は無いし、禁煙になりそうな電子タバコとかから始めてみようかな?などと考えながら、プシュっ、グビグビ。
そして、やっと気付きました。
飲み過ぎやないか!
禁酒チャレンジ開始
怪我の回復と節約。こうして、禁酒チャレンジが始まったのです。
自分で言うのも何ですが、あの酒好きの男が1週間以上飲んでない事に敬意を表したいです。
今は、炭酸水のレモン味にしてます。
暑くなってきたので、やはりビールが飲みたくなります。
そこで、炭酸にすれば誤魔化せるんじゃないか?という発想からコレにしました。
そしてその発想は今のところ成功です。
意外にも体が酒を欲してきません。
3日ほど経過した頃には、朝から頭がスッキリしている事に気づきました。
これは・・・?イケルかもしれない。
※強炭酸水。侮るなかれ!美味いっす。
身体に異変が…
そして1週間が過ぎて異変が発生します。
最近上映された「名探偵コナン~隻眼の残像」を家族で見に行きました。
始まって間もなく腹痛が…。トイレへ急ぎます。
そして終盤、またも腹痛。必死に耐えます。
今作、**かなり面白い!**すごく格好いいのです!だから、必死に耐えます。
早く、コナン君…。早く、解決して…。毛利小五郎…。
無事に最後まで見終えて、すぐにトイレへ。その後も、何だかよくわからない腹痛に苦しめられていました。
それと別件で、車の乗り降りするたびに何度も静電気が発生!
これにも参りました。
私はこれまで生きてきて、数えるほどしか静電気の発生を経験した事がありません。
「乾燥してる」と言われる季節も私には関係のない話でした。

まさかの禁酒の副作用
中年になって体内の水分が減ったのか?ついに私も乾燥肌という物になっていくのか?
と思っていたのですが、調べて分かりました。
この異変は、どちらも禁酒による初期症状だったのです!
皆さんは知ってましたか?
散々、飲んできた私は、アルコールによって水分量が保たれていたのです。
調べたことまとめ
- 酒は一時的に体に水分を引き込む働きがある
- ただし利尿作用があるので最終的には「脱水しやすい」
- 長期的飲んでると体が水分多めに慣れている
- これを急に断つと、体が乾きやすいモードにシフトする
- しかも水分摂取が少ないと、さらに乾燥が進みやすい
さらに他にも色々ありましたが、
- アルコールが腸を刺激する働きがなくなり、腸の動きが鈍る場合がある。その結果、便秘や下痢っぽくなる事もある
- 通常、2~3週間で落ち着く
とのことでした。
そうか~、変な病気じゃなくて良かった。
まとめ
禁酒って、ただ「飲まない」だけじゃなく、
体にも心にもいろんな変化が起こるんですね。
もしあなたも「やめたいな」と思っているなら、
炭酸水レモン味、おすすめですよ!
そして、最初の腹痛や静電気にビビらず、
2~3週間は頑張ってみてください。
一緒に、少しずつ、真人間になりましょう。笑
※この記事はあくまで筆者個人の体験談です。禁酒・減酒は体調を見ながら無理なく進めましょう!





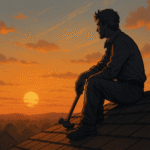
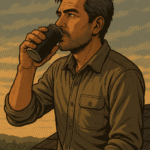
コメント